

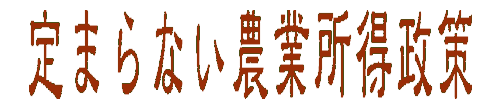
2001年
直接所得補償で揺れる中山間地域
「農業を取り巻く環境が厳しいなか、5年間の営農継続を、集落単位でどう確保しろというのか」
中山間地域への直接所得補償、いわゆる条件不立地に対する所得補助の直接支払いをめぐって今、その対象になるべき地域が揺れている。2000年度から実施された中山間地域に対する所得補助の直接支払いは、農水省が当初予定していたものよりも受け取る地域が大幅に減った。
新農業基本法のひとつの目玉として登場した日本型デカップリングだが、初年度の直接所得補償の申請は、全国で予定していた面積の約6割にしか満たなかった。農水省では、初年度の全国での対象面積を90万ヘクタールとし、330億円を予算化したが、蓋を開けてみれば実施面積は56万7000ヘクタールにとどまり、対象市町村2158のうち、実施市町村は1690で、しかも、当初見込み面積の半分にも満たない実施市町村が都道府県では21にものぼった。中山間地の直接所得補償とは、生産条件が不立地な地域に対する格差是正のため、その地域の生産コストを助成金で賄うもので、政府が農家に補助金を直接支払う、というもの。1975年にEU(欧州連合)が条件不立地対策として導入したのを参考に、日本型として成立させようと、2000年度から実施された。ただ、補助金漬けの従来の農業政策に対しては批判が強いため、農山村が持つ景観を含む多面的機能を保持するために、生産条件が他地域より不利な地域に限り、耕作放棄地の増加を食い止めるなどの策として、助成金により、その地域の農家所得を補填する、とした。
そして、生産条件が他地域より不利な地域を傾斜角の厳しい農地などとして、補助対象を、永続性のある営農ができるように集落ごとに営農協定を結び、5年間は営農継続が可能なところ、とした。しかし、現実にこの条件を満たし、徹底を図ろうとすると、畑地や果樹園などは、水田と比較して交付金の単価が低く、傾斜基準も厳しい。「となれば、誰がそのきつい傾斜地での継続営農を確約できるというのか。おまけに同じ地域の中で、対象になる農家とならない農家がでるとなれば、集落営農そのものも理解を得ぬくい、というのが実情だ」と、中山間地のなかでも特に過疎化が進む山間地域の町村の担当者は嘆く。
加えて農家からは次のような解釈が出され、農家保護を謳い文句にした日本型デカップリングは、あまり受けが良くない。
「直接所得補償という言葉の響きには正直、期待を寄せるものがあったが、実施される段になって、その内容を聞いてみると、結局は、補助金で集落全体に縛りをかけるようなもの。これまでの誘導政策と大差はない。むしろこれまで以上に農政に従順な集落を確保しようとしているかのようで、釈然としない」そう農家が思うのも無理はない。なぜなら、直接所得補償を受けようとすれば必ず、その集落全体の農家が一体となった「集落営農協定」を結ぶ必要があると共に、集落の農地を集約化しなければならない。いわば一農家という存在ではなく、その集落単位を一つの縛りとして、その集落全体の農家を1営農の単位とするというものだ。そして、農地がつながっていなくても1ヘクタール以上の営農を、集落が一体となって行なうことも条件化されている。このため、解釈の仕方次第によっては、直接所得補償という「おいしい文言」で農家を誘い、今後はどんなにその地域にマッチしない農業政策でも、有無を言わさずに、受け入れさせる環境を整備しようとしているとも受け取れるからだ。
しかし、農政側の現実は、農家がどう解釈しようとも公共土木工事が可逆性を持ち得ないのと同様、一度動き出したデカップリングを後戻りさせることはできない。そして、現実問題として条件不立地での農家の高齢化はとどまることを知らず、離農などにより耕作放棄地も増加の一途を辿っている。このまま手をこまねいているだけだと、農地の荒廃に拍車をかけるばかりだ。
農業政策を遂行する側は「その集落での営農協定が無理ならば、他集落と合同で広域に協定を結んだらどうか」「担い手となる人がいないのであれば、普及所や農協などが力を貸す」などなど、あれやこれやの代替策も提示して集落営農協定に結びつけようと躍起にならざるを得ない、という現実もある。
しかし農家サイドは「これまでと同じで、これから農協や普及所がどう役立つというのか。役立っていたのなら農業を取り巻く環境はこうまでなっていなかったはずだ」と厳しい。
農水省と足並みをそろえて集落営農の推進に取り組むJA全中(農協中央会)も「地域で営まれる集落営農は、大規模農業法人や規模拡大農家とならぶ重要なもので、これこそが担い手だ」と、その必要性を唱えるが、これに対しても農家は「農協に従順な担い手や地域リーダーだけの価値観で束ねようとする農政の片棒かつぎという思いは否めない」と、眉ツバもの的認識を示すなど、なかなか現実には複雑な側面ものぞかせている。条件不立地の格差是正のために誕生したばかりの日本型デカップリング、直接所得補償はいま、動き出したばかり。
この制度が農村や農家のためになるのか否かの回答が出るのは、まだまだ先の話だが、数々の矛盾をどう整理し、どう道筋をつけていくのかが、21世紀の皮切りに際して重要な課題になっている。(2001,2/9)減反で減収に拍車、手詰まりの米の価格政策
「農家への所得政策と言えば、補助金で手厚く保護しているというイメージを植え付けたいのだろうが、実際には何だ、これは」
農水省が示した2001年の米の生産調整、いわゆる減反計画に対して唖然とする稲作農家は多い。
米価格の低迷などによる経営環境の悪化は深刻で、特に米オンリーで大規模化を進めてきた農家の収入は、毎年100万円単位で減っているのが現状だ。その状況にトドメでも刺すかのように、減反面積をさらに4万7000ヘクタールも拡大するというのだから、稲作農家が唖然とするのも無理はない。
農水省や農協が示す減反の理由は簡単で、米在庫の過剰感が米価格の低下をまねいているので、過剰感を払拭するために減反をして米の生産量を少なくする、というもので、米在庫が減ればその分、米の価格が上昇するという判断だ。一般的にみればそれには違いないが、米の価格が上昇したところで、稲作農家個々の作付け面積が減れば、当然のこととして1軒の農家の栽培量が減り、そのことにより1軒の農家の出荷量は減る。そして、出荷量が減る分、1軒の農家が販売した米の総手取り額も減るというのが普通だ。米を減反して転作に励み、転作助成金や追加助成を受けても、農家の懐に入ってくる額はしれている。むしろ、諸々の費用を差し引けば、赤字が膨らむ場合も無きにしもあらずだ。
「1軒の農家の収入が減っても、米相場の金額が低下しなければ良しとする判断はおかしい」と、農水省や農協が示す米の生産調整の理由に首をかしげる農家は多い。2000年産米の際には、96万3000ヘクタールが減反面積として割り当てられた。その時の農水省や農協の説明は、「米の年間消費量は農家消費込みで約930万トンなので、895万トンになるように設定した減反面積で、需要よりも生産が下回ることから、米の価格は上昇する」というものだった。しかし、現実には米の価格は低迷したままだ。
「なのにこれが最もいい方法だというのだから、苦笑せざるを得ないし、考えた面々の知能も疑うというものだ」と、稲作農家の判定は厳しい。減反に従っても米の価格が低迷し続ける理由を農水省や農協などは「現実には豊作で、米の在庫調整が思うようにいかなかったし、消費者の米離れもある」とする。だから「2001年産の米の生産量をさらに25万トン減らし、需要量より供給量を少なくする。そのためには、面積としてさらに4万7000ヘクタールの減反が必要だ」とした。そして、豊作によるダブつきを制御するために、減反に加えて「需給調整水田」を設定。豊作で作況指数が100を超える場合は、米が出来上がるまえに刈り取って、それを飼料用米にするという苦肉の策も打ち出した。
しかし、「現実には豊作で、米の在庫調整が思うようにいかなかった」とする2000年産米も、この余剰分の25万トンは、政府が買い入れて市場から隔離して需給調整をしているのが実態で、実質には64万トンを「緊急総合米対策」として市場から隔離。そうしてもなお現実には、米の価格は低迷しているというのが実情だ。
「米の市場からの隔離に続いて、青刈り用の田んぼの用意と、米を手当てする側から見れば、需給調整で市場から米を隔離すればするだけ過剰感が増すという心理が働くのに、それが分からないようだ」と米卸サイドからは、こうした対策を疑問視する声もあがる。例え、減反のリスクを軽減するために「稲作経営安定対策」を筆頭にする助成金で損益が補填されていたとしても、米の生産現場では、「わりに合わない」とする声が多いのも現実だ。そして、「百歩譲って、小規模農家を切り捨て、大規模農家や認定農家だけでこれからの農業は十分という判断を認知するにしても、米政策はあまりにも展望がなさ過ぎる」との声も多い。
無理はない。過去、農業者は、農業政策に順応して「米の増産」と言われればそれに従い、「単作化」と言われれば大豆や飼料用穀物の生産をやめ、「減反」を指示されれば減反に励んできた。そして、その通りにすれば、農業経営は安定すると思い込まされてきた。
しかし、現実には、農業経営は一向に上向かない。実際に、公的資金で手助けする代表的な経営資金の「農業近代化資金」にしても、米価の下落や米の生産調整(減反)の拡大など、米情勢の深刻化で、有利な制度融資が用意されていても、利用率は低く、農家の投資マインドは冷え込む一方だ。これからの農業の担い手として農水省や農協などが位置付ける大規模農家や認定農家になればなるほど、「米価の底が見えない中では、設備投資についても、様子見を決め込む以外にない」とする判断が強く、これからの担い手に勢いがないのも実情だ。
しかし、意欲が減退しているとはいえ、担い手といわずとも、個々の農家にとっては、設備や農機具の老朽化に伴って定期的にやってくる買い替え時期を迎えれば、投資は避けて通れないのも現実だ。
その現実に対しては「当面は、買い替えを見送り、改修できるものは修理や機械整備でしのぐのが賢明」とする判断が強い。政府や農協組織の小作ではないのにもかかわらず、半強制的に政策を押し付けられる農業現場は、新しい世紀を迎えてなお一層、混迷の度合いを深めているかのようだ。
米価が低迷を続け、農業を取り巻く経営環境の悪化が、日増しに強くなっているなか、今年もまた、本格的な耕作シーズンを前にして、米の減反面積が転作で揺れながら着実に割り当てられている。(2001.2/27)※以後、随時これからの動向を掲載していきます。
●バックナンバー関連記事「揺れる減反政策」
●バックナンバー関連記事「戦後日本の農業政策」